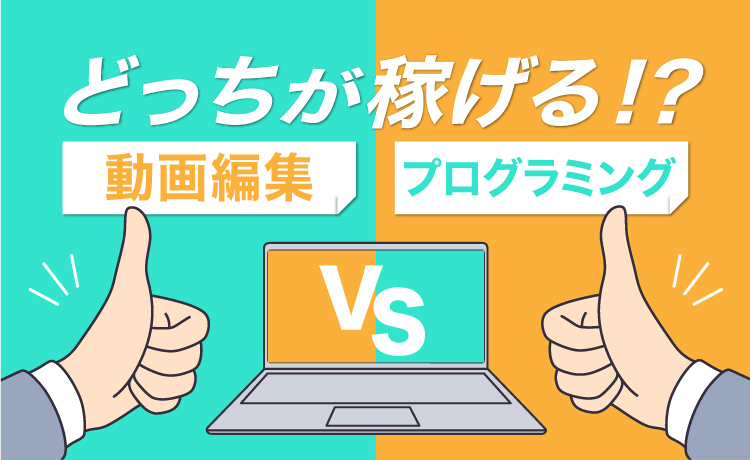この記事でわかること
- 動画編集と著作権の基本的な知識
- 著作権侵害のリスクと具体的な例
- 著作権発生のタイミング
- 著作権に違反しないための動画編集の方法
- 動画編集で著作権に引っかからないために許可を取る手順
- 動画編集で著作権トラブルを避けるために確認するべきこと
- 動画で著作権に対応した注意書きの例文
動画編集における著作権の領域は、一見すると難解に見えるかもしれません。
しかし、著作権とは、一体「どこまで」が問題なのか?
YouTube動画やアニメの編集で押さえておきたいポイントとは何なのか?
動画に使用する音楽はどの程度まで許されるのか?
そんな混乱を解きほぐす冴えた解説をこの記事では提供します。
また、動画の二次利用とは何を意味し、引用が可能なケースとその方法も押さえたいところ。
さらに、動画で使われる著作権の注意書きやその例文、表示法についても触れることで、ガイドラインの理解を深めます。
この記事を通じて、法律に触れることなく、創造的なコンテンツを安心して作り出すことができるようになるでしょう。
今すぐ読み進めて、あなたの動画編集スキルを新たな次元に引き上げましょう。
動画編集と著作権の基本的な説明

映像コンテンツの製作業界において、必要な基本的な理解として、動画編集と著作権の関連性があります。
ここでは、著作権とは何か、著作権法の概要、動画編集での著作権の位置づけ、そして動画内容と著作権の関連性について詳しく解説していきます。
著作権とは何か
著作権とは
- 楽曲
- 映像
- 小説
などの著作物を創造した著作者が持つ経済的及び精神的利益を守る権利のことを指します。
著作権法によって保護され、他人が無断で複製や公開することを禁じています。
また、著作物に登場する
- キャラクター
- 商標
- ロゴ
なども著作権の対象となります。
著作権情報は一部の音源などでは、JASRACが管理しています。
著作権法の概要
著作権法は、著作物の創作者がその創作物を自由に使うことを保証し、他人による無断利用を禁じる法律です。
制作した作品に対して
- 複製権
- 公表権
- 翻訳権
などの権利が帰属されます。
また、肖像権や著作者人格権なども含まれます。
動画編集における著作権の位置づけ
動画編集作業においては、使用される映像や音楽素材などが著作物となり、それらの管理者から許可を得ることが必要になります。
もし許可なく使用した場合、著作権侵害となり
- 法的な問題
- 罰金
に繋がる可能性があります。
そのため、動画編集の際には著作権の理解と適切な取り扱いが重要になります。
動画内容と著作権の関係性
動画の内容には
- 映像
- 音楽
- キャラクター
などの著作物が含まれます。
これらの著作物を利用するには、著作権者からの許可が必要となります。

自身で撮影した映像や作成した音楽であっても、登場人物の肖像権や建物の商標権を侵害してしまう場合もあります。
そのため、動画の内容を考える際には、著作権の存在を十分に認識し、法律に抵触しないよう注意が必要です。
著作権侵害の具体的な例
一例としてBGM著作権の侵害がよく見られます。
人気曲を動画のBGMとして使用した場合、それが著作権者からの許可なく、しかもその動画が一般に公開されている状態では、明らかに著作権の侵害にあたります。
なお、有名曲は勿論、マイナーな曲であっても、その音楽そのものが著作権フリーで無い限り同様です。
公開する動画に
- 写真
- イラスト
を使用する場合も注意が必要です。
たとえそれがインターネットで手に入る画像であっても、画像使用許可を得ていなければ、それもまた著作権違反になりかねません。
他人の作品を勝手に使用せず、必ず著作権フリーの素材を活用することが大切です。
さらに忘れてはならないのが、著作権侵害の見逃されやすい要素
- オープニング
- エンディング
です。
人気アニメや映画のオープニング、エンディングを模倣した動画を公開する行為もまた、著作権侵害に該当する可能性があります。
あくまで個人利用の範囲内であれば問題ないですが、公開の場で流すことは避けたほうが無難です。

これらの著作権侵害は法律的に罰せられるだけでなく、信用の失墜を招く可能性もあります。
オリジナルの動画編集を心がけ、著作権についての理解を深めていくことが求められるでしょう。
著作権がひっかかる動画はどこからどこまで?

インターネットの普及により、誰もが手軽に情報を発信できる時代となりました。
しかし、その中には著作権を無視した動画配信も散見されています。
「あれ?この動画って大丈夫なの…?」と感じたことはありませんか。
動画に映る一つひとつが著作権の対象になりえるとしたら、どこまでが許されて、どこからが侵害にあたるのでしょうか。
ここからは、そんな疑問を持つ方々へ向けて、著作権の基本知識から解説します。
著作権発生のタイミング
そもそも、著作権が生じるためにはどのようなタイミングが求められるのでしょうか。
その答えは、「創作・公表された瞬間」です。
個人が書いた
- 小説
- 描いた絵
- 作った音楽
など、創造的表現の結果が具現化された時点で、その著作物は著作権によって保護されます。
例えば、スマホで撮影した動画も、撮影した人の著作権が発生します。
公に見せるために作られたり、他人に見せるために撮影されたりする必要はありません。
創作し、形にした瞬間からその著作物は著作権の対象となるのです。
しかし、注意が必要なのは、著作権が発生している物を編集したり、改変したりした場合です。
例えば、誰かが撮影した動画をスマホのアプリで編集したとしましょう。
その動画の改変は、その理由に関わらずオリジナルの著作権を侵害する可能性があります。

結婚式のビデオ撮影などで、他人の作品が含まれた場合も複雑な問題が起きうるに留意が必要です。
これらの事情は、まさに著作権発生のタイミングを理解する上でも重要なポイントと言えるでしょう。
著作権の期間
次に、著作権がどれくらいの期間続くのかについて説明します。
著作権の保護期間は原則として「著者の死後50年」でしたが、2004年の改正で「著者の死後70年」に延長されました。
そしてこの期間が過ぎると、その作品はパブリックドメインとなり、著作権の制約なく誰でも自由に利用できるようになります。
しかし、この期間内にあっても、使用許諾を得ればその作品を利用することは可能です。
例えば、動画編集において他人の作品を用いたい場合、その作品が著作権期間内であっても、著作権者から使用許諾を得れば利用が可能となります。
ただし、その際には料金が発生することもあるため
- 具体的な利用方法
- 料金
などについては事前に確認が必要です。
音楽の使用においても同様で、
例えば
- 結婚式で使用する音楽
- ポートフォリオで使用する音楽
などは、著作権者から許可を得て使用することが求められます。
その際には
- アップルミュージック
- その他の音楽配信サービス
で提供されている音楽についても、個人的な楽しみとして使用する場合と、公に放送する場合とで著作権法が異なります。
そのため、それらの法律を理解して適切に利用することが必要です。
公衆送信権とは
次に、「公衆送信権」について説明します。
公衆送信権とは、著作権法における著作権者の権利で、インターネットのように多くの人がアクセスできる場所に作品を公開する権利を指します。
- 自分が作った音楽をYouTubeにアップロードする
- ブログに自分が描いたイラストを掲載する
など、誰でも自由に見ることができる形で作品を公開する際には、この公衆送信権が適用されます。
つまり、あなたが動画編集アプリで作成した素晴らしい作品をYouTubeにアップロードする際、その動画に含まれる
- 映像
- 音楽
- テキスト
などの著作物について、その公衆送信権を確認する必要があります。
それらの著作物の著者から
- 公衆送信の許諾を得ているか
- それらの著作物がすでにパブリックドメイン(著作権が存在しない状態)になっているか
などを確認しなければなりません。
この公衆送信権は
- 結婚式のビデオ
- 帰省の思い出動画
- 自分の製作過程を記録したポートフォリオ
など、身近な場面で問題となることがあります。

たとえば、アップルミュージックから音楽を取り込んで結婚式のビデオに使用した場合、その公衆送信権は著作権者が保持しているため、その使用には著作者からの許可が必要となります。
結婚式のビデオをネットに投稿したり、公開したりする際には、こうした事情を把握し、必要な手続きをおこなうことが求められます。
二次利用と著作権
さて、著作権のうち特に紛らわしいとされる領域が「二次利用」です。
これは、もともとある作品を元に新しい作品を生み出す行為を指し、この場合の著作権法は少々複雑です。
二次利用を考える際にまず留意しなければならない点は、元となる作品の著作権に触れる可能性があるということです。
例えば、他人が撮影した動画を勝手にダウンロードし、それを元に新たな動画作品を作る場合、その動画の著作権者から許可を得ていなければ、その行為は著作権侵害となりえます。
動画編集で音楽使用時の二次利用
また、音楽を使った動画編集も同様です。
たとえば、結婚式のビデオに流すために映画のサウンドトラックを使用するという場合、その音楽の著作権者から許可を得ていなければ、これは法的な問題となり得ます。
アップルミュージック等からダウンロードした音楽を使う場合も同様で、その使用目的により著作権侵害になり得ます。
二次利用のルール
一方、自分の創作物を他人に二次利用してもらう際も注意が必要です。
例えば、あなたが制作した動画が他人のポートフォリオ作成の素材となる可能性もあります。
その場合、あらかじめ自分の作品についての二次利用のルールを明確にしておくことで、予期せぬトラブルを避けることができます。
動画編集での著作権侵害のリスク

動画編集における著作権侵害のリスクについて、知識を持つことは、トラブルを事前に防ぐ重要な要素です。
- 映像素材
- 音楽の著作権問題
- 動画投稿サイト
などでの著作権法違反、罰則や法的リスクについて詳しく説明します。
サウンドエフェクトや音楽の著作権問題
BGMやサウンドエフェクトにおいても、著作権が存在し、その権利者から使用許可を得る必要があります。
特に楽曲については、著作隣接権という演奏家や製作者の権利も存在しますので、それらの許諾を得ることも十分に考慮しなければなりません。
動画投稿サイトでの著作権法違反
動画投稿サイトでは、自己表現の場としてビジネスや個人が利用しますが、他人の著作物を使用した映像を無断でアップロードすることは著作権侵害に当たります。
著作権侵害が発覚した場合、投稿した動画は削除され、アカウントの凍結や法的問題を引き起こす可能性があります。
動画投稿サイト利用者が犯しやすい著作権法違反
よくある著作権違反として、音楽や映像作品の無断アップロードが挙げられます。
- 公開された映画のワンシーンを抜き出す
- そのまま投稿する
- 著作権フリーではない音楽を背景音として利用する
上記の場合等は、すべて著作権法違反となる可能性が高いです。
ただし、動画作成者自身が全ての素材を制作し、全てオリジナルの動画を作成した場合、著作権法違反の心配はないことを念頭に置いておきましょう。
しかし、動画内で他人の著作物を引用する場合は、都度許可を得た上で使用しなければならないところ、注意が必要です。
重要なのは、知識不足からくる違反行為を避けること。
求められるのは
- 著作権法について正確な知識を持つ
- 他者の著作権を尊重する
上記のことを意識しながら未然に違反を防ぐには、著作権法の知識を学び、理解することが非常に重要な一歩と言えるでしょう。
罰則や法的リスクについて
著作権は動画の音楽や映像、そしてストーリー等も含まれ、それらを許可なく使用することは違法行為になり、罰則の対象となり得ます。
法的には
- 損害賠償
- 罰金
- 懲役が科される
可能性があります。
肖像権
次に忘れてはならない法的リスクの一つが肖像権です。
人物の顔や声、その他特徴的な姿を無許可で利用することは、侵害となります。
許可を得ないで使用した場合、損害賠償請求を受ける危険性が存在します。
そうしたトラブルを避けるためにも、事前に許可を得る等の配慮が必要です。
プライバシーの侵害
プライバシーの侵害も重要な法的リスクです。
特定の個人や組織の私的な情報を公にすることは問題となります。
例えば、他人の連絡先や住所などを無断で公開すると、プライバシー侵害となり、罰ばれます。
名誉毀損
最後に、名誉毀損も覚えておくべき法的リスクです。
他人を中傷する内容の動画は法的問題となり、罰金や損害賠償を求められることもあります。
誹謗中傷する内容の投稿は避け、公正な視点を持つことが大切です。
動画編集における法的なリスクは以上の通りですが、初心者を始め多くの方々が無自覚的に侵害する可能性があるため、注意が怠れません。
独自のコンテンツを作る際は法律を理解し、適切に対応することが重要となります。
著作権に引っかからない動画編集の方法

著作権を理解し、遵守する方法としては、フリー素材の利用、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス、著作権を確認する方法、許可を取る手順、引用と著作権について学んでいきましょう。
フリー素材の利用方法
フリー素材を上手に利用し、著作権を遵守した動画編集をするための方法を紹介いたします。
初めに考慮すべきはフリー素材の選び方です。
クリエイティブ・コモンズライセンスと呼ばれる制度を理解し、正しく利用することが大切です。
このライセンスは、著作権者が自分の作品を他人が使用する条件を設定できる制度であり、フリー素材にもさまざまな種類が存在します。
- 商用利用可能なもの
- 改変自由なもの
など、素材によって利用条件が異なります。
そのため、自分の目的に合った素材を選ぶことが求められます。
フリー素材を使用する際の注意点
フリー素材を使用する際の注意点として、素材の出典を明記することが挙げられます。
利用条件によっては、出典の明記が必須となっているものも多いです。
- 利用した素材が本当にフリーであるか
- ライセンスが適正に管理されているか
などを確認することも重要です。
最後に、自分で撮影した映像や音声を使用する場合でも、他人の肖像権やプライバシーを侵害しないよう配慮が必要です。
撮影する人物や場所に許可を取ることをお忘れなく。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは、著作物の利用範囲を著作権者が自由に設定できるライセンス体系です。
著作権法に基づく権利を一部保持しつつ、特定の条件下で第三者に対して利用を許諾することが可能になります。
このライセンス体系は、多種多様な表現活動が行われる現代社会に対応すべく、クリエイティブ・コモンズという非営利団体によって策定されました。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの特徴
その特徴は、6つの基本ライセンスから選択できる点にあります。
具体的には
- 利用者に対するクレジット表示義務
- 商用利用の許可・禁止
- 二次創作の許可・禁止
- 二次創作物の配布形態に関する条件
などを組み合わせることが可能です。
こうした選択肢の広さが、個々の著作権者が自身の作品をどのように流通させるかを自己決定できる自由度を生み出しました。
この結果、伝統的な著作権法が抱える課題を解消し、ものづくりの活性化を目指す方向性が打ち出されています。
しかし、注意点として、一度設定したクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは基本的に変更することはできません。
そのため、設定する際には慎重な判断が求められます。
著作権を確認する方法
著作権を確認する方法として
- ダウンロードサイトや配信サイトで提供されている著作権情報
- 直接提供者へ問い合わせる
- 法律専門家のアドバイスを得る
等が挙げられます。
ダウンロードサイトや配信サイトで提供されている著作権情報
まず初めに、自身が使用しようとしている素材が、どのようなライセンスのもと提供されているのかを確認することが求められます。
具体的には、素材の提供元のウェブサイトや使用証明書を確認し、特定のライセンス(例えばクリエイティブ・コモンズなど)が適用されているか、または特に制限が設けられているかを見つけましょう。
これらの情報は、通常、素材のダウンロードページや詳細情報セクションに記載されています。
直接提供者へ問い合わせる
- 著作権情報が明記されていない場合
- 独自のライセンス適用がある場合
上記の場合には直接提供者へ問い合わせるのがベスト。
使用目的や範囲を具体的に伝え、使用許可を得られるか事前に確認します。
これにより法的トラブルを未然に回避すると共に、自身の作品が合法的なものであることを明確にすることができるでしょう。

著作権フリーと明言されている素材でも、その範囲が無制限であるわけではないため、細部の使用条件を把握することが重要。
特に商用利用や二次的著作物の制作には、条件が付く場合が多いため、尊重と透明性を維持することで創作活動はより豊かで公正なものとなります。
許可を取る手順
他人の著作物を使用する際には、その著作権者から許可を得る手続きが必要になります。
許可を得るためには主な必要事項としては
- 著作権者や権利管理団体への連絡
- 使用申請
- 使用料の支払い
などが必要な場合があります。
具体的な手順を見ていきましょう。
1.使用したい素材が著作権保護の対象であるか確認する
初めに行うこととなるのが、使用したい素材が著作権保護の対象であるか確認すること。
一般的に音楽や映像、イラストなどは著作権法により保護されています。
しかし中には著作権フリーの素材も存在しますから、まずその辺りを確認しましょう。
2.著作権を保持している個人や企業に連絡を取る
続いて行うべきは、著作権を保持している個人や企業に連絡を取ること。
使用許可を求めるには
- その素材の著作権者に具体的にどのような形で利用したいのか
- どの程度の範囲で利用予定か
といった内容を伝える必要があります。
3.文書で許可内容を残す
承諾を得たら、その旨を文書で残すことが大切です。
電子メールのやりとりでも構いませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、許可の証となる文書を保存しておくことをおすすめします。
4.使用許可を得た素材の出典・著作権者を明示する
最後に、動画内やクレジットにて、使用許可を得た素材の出典・著作権者を明示することを忘れてはなりません。
利用者が一目で著作権者を確認できるよう、視認性高める配慮が求められます。
以上が動画編集で著作権の許可を取る手順となります。
著作権法は複雑で逐一変更もされますので、最新の情報に常に目を向け、適切な手続きを行うように心掛けましょう。
引用と著作権
引用は、他人の著作物を自身の表現の一部として使用する方法で、引用の要件を満たせば著作権を侵害しない例外として認められています。
しかし、引用する際にもその要件を満たさなければならず、適切な引用方法を理解し、用いることが重要です。
著作権を侵害しない動画編集の方法

現代社会において、動画投稿や動画制作は個人でも業者でも気軽に行えるようになりました。
しかし、その一方で“著作権問題”という大きな壁が立ちはだかります。
著作権料を支払わない限り、他人の創作物である画像や音楽、映像などを無断複製し、自分の作品に使用することは法律で禁じられています。
では、どのようにすれば著作権を侵害せずに動画編集ができるでしょうか。
ここでは、著作権フリーの素材活用やライセンスについて説明し、著作権に配慮した動画編集の手法を探ります。
著作権フリーの素材の利用
まず考えるべきなのは、著作権フリーの素材を利用する方法です。
- 映像素材
- 音楽
- 画像
- テキスト
など多岐に渡ります。
たとえば、フリー映像素材は映像編集の際に背景や挿入シーンとして使えますし、BGMなども著作権フリーの音楽を使うことで、音楽著作権の問題から逃れることができます。
一方、著作権フリーの素材を探すためには
- 専門のウェブサイト
- データベース
などを活用するのが一般的です。
ただし、重要な点として、提供元のプライバシーポリシーをしっかりと読むことが求められます。
素材探しの際には、必ず使用許可の範囲や条件を確認しましょう。
クリエイティブ・コモンズライセンスの活用
次に、クリエイティブ・コモンズライセンスについて解説します。
このライセンス制度は、著作者が自分の作品を自由に利用してもらうことを前提に提供するためのもので、著作権適用範囲を縮小できる特徴があります。
具体的な内容は著作者によって違いますが、一部利用に対する許可が包含されていることが一般的です。
クリエイティブ・コモンズライセンスとは異なり、全ての作品が著作権フリーであるわけではありません。
使用する前にそのライセンスが
- 何を許可しているか
- 何を禁止しているのか
を確認しましょう。
多くの場合、クレジット表記が必要となるため、その点も把握しておくことが大切です。
パブリックドメインの活用
さらに、パブリックドメインについても触れておくことが重要です。
パブリックドメインとは、著作権の保護期間が終了した作品や著作者が著作権を放棄した作品のことを言います。
これらの作品群は誰でも自由に使うことができます。
パブリックドメインの作品は
- 映画
- 音楽
- 文学
- 画像
など多くの分野にわたります。
パブリックドメインの作品を使用するメリットとしては、その自由度の高さが挙げられます。
著作権の制約を受けずに自由に利用できるため、どんな映像制作ソフトでもそのまま使ったり、自分の意図に合わせて編集することが可能となります。

必ずしも全ての作品がパブリックドメインであるわけではないため、使用する前にその作品が本当にパブリックドメインであるのかを確認することが肝心となります。
動画編集のコツとポイント
ここからは、著作権侵害を防ぎつつ、効果的な動画編集のコツとポイントについて説明していきます。
しっかりした構成や計画性
まず、映像編集にはしっかりした構成や計画性が求められます。
そのため、あらかじめ脚本を書くなどして、どのシーンで何を伝えたいのかを整理しておくことが大切です。
映像の質
次に、映像の質にも注目しましょう。
素材を探す際や撮影を行う際は、クリアで鮮やかな映像を心がけることが大切です。
そして、映像だけでなく、音も重要です。
著作権に配慮したBGMを選ぶようにしましょう。
さらに、可能であれば、オリジナルの音楽を作ることもおすすめです。
編集技術
最後に、編集技術について述べておきます。
素材を組み合わせてストーリーを作る際には、リズム感を大切にすることが重要です。
また、視覚効果やトランジションの使用も、視聴者の注目を引きつける手段となるでしょう。
ただし、これらの技術は適度に使用することが重要で、余計な装飾は視聴者を混乱させる可能性があります。
著作権に配慮したBGMの選び方
最後に、著作権に配慮したBGMの選び方について解説します。
まず、BGM著作権とは音楽の作者が法律上認められた権利のことで、無断で使用すると違法となるため注意が必要です。
そのため、動画にBGMをつける際にも
- 著作権フリーのもの
- クリエイティブ・コモンズライセンスが許諾するもの
を選ぶことが推奨されます。
さらに、BGMの選び方では、その動画の内容やイメージに合ったものを選ぶことが重要です。
例えば、静かな自然の風景を撮影した動画には、穏やかな音楽が合い、スポーツ系の元気な動画には、アップテンポな音楽が良いでしょう。
また、視聴者の気持ちを盛り上げるためには、音楽のリズムやメロディも大切な要素となります。
最終的には、あなた自身が動画を見て感じたことや、伝えたいメッセージを大切にしながら音楽を選んでいきましょう。
著作権の注意書きの書き方

多くの人が著作権について誤解を持っており、それが著作権侵害につながることもあるため、著作権の注意書きの書き方について適切な知識を持つことは非常に重要です。
ここでは、著作権の表記の仕方、動画内での注意書きの位置、そして動画の著作権に対応した注意書きの例文について見ていきましょう。
著作権の表記の仕方
著作権表記には特定の形式が存在します。
まず、「©」や「Copyright」を使った表記が一般的です。
これらの記号の後には発刊年、著作権者の名前を記載します。
例えば、© 2022 山田太郎のように表記することで、その作品が山田太郎によって2022年に発行され、彼が著作権を保持していることが明確になります。
ただし注意が必要なのは、このような表記は著作権を保持するための法的な必要条件ではないという点です。
著作権は作品が創作された瞬間に自動的に発生します。
しかし、著作権表記を行うことで、他人が誤って著作権侵害を行うことを防ぐことができます。
動画内での注意書きの位置
動画内での著作権の注意書きは、視聴者が容易に読むことができる位置に配置すべきです。
動画の最初または最後、あるいは両方に表記するのが一般的です。
また、動画全体を通して著作権のクレジットを表示することも可能です。
視覴覚的な媒体である動画では、文字だけでなく音楽や映像を使ったクリエイティブな表現も可能です。
著作権表記は視認性が高く、見逃されないようにすることが重要です。
しかし、視聴者の視線を邪魔せず、動画の内容を損なわないように配慮することも必要です。
動画で著作権に対応した注意書きの例文
現実の世界でもデジタルの世界でも、著作権に対応した注意書きは誤解や問題を防ぐ重要なツールです。
そのため、その表現方法には適切な配慮が必要です。
動画コンテンツに関して、以下に例文を挙げます。
- 「このビデオの内容(映像・音楽・文字)は著作権法により保護されています。無断での複製や使用は禁じられています。」
- 「本動画内の全ての素材(映像・音楽・テキスト)は、著作権者が保有する著作権により保護されております。無断複製、無断転載、無断使用は固くお断り申し上げます。」
以上のような表現を使うことで、視聴者に対してあなたの動画が著作権により保護されていることを明確に伝えることができます。
また、使用される素材や情報源に対して著作権を尊重する姿勢を示し、それが視聴者による信頼の形成に繋がります。
著作権の存在は創作者の労働を保護するもので、それに基づく表記は公正で適切な情報共有を助け、著作権違反を防ぐ最初のステップとなります。
動画編集で著作権トラブルを避けるための対策

ここでは、動画編集で著作権トラブルを避けるための対策を詳しく紹介します。
YouTubeなどの動画投稿サイトで注意すべきポイントから、前例を参考にしたベストプラクティスまで、具体的な対策をわかりやすくお話していきます。
YouTubeなどの動画投稿サイトでの注意点
具体的な注意点としては、他人の楽曲や映像を無許可で利用することは厳禁です。
また、他人の著作物から派生した作品であっても、改変やアレンジが必要となります。
- 商標権
- 肖像権
などにも注意が必要で、無許可での使用は避けるべきです。
著作権フリーの素材を使用する場合でも、ライセンス条項を確認しましょう。
クリエイティブ・コモンズなどのライセンスが適用されている場合、それぞれに独自の使用条件があります。
多くの場合
- 商用利用が可能か
- 元の作品をどの程度改変できるか
- 作品にクレジットを記載する必要があるか
など詳細なルールが定められています。
著作権侵害の訴訟事例
著作権を守ることの重要性をよく示す事例として、以下に具体的な訴訟事例をいくつか紹介します。
自分の楽曲を無断使用され、著作権侵害で訴えた事例
まず、大きな影響を与えた事例として、著名なミュージシャンが非営利活動のイベントに自分の楽曲を無断使用され、著作権侵害で訴えたケースがあります。
この事例では、主催者側が非営利であるという理由だけで許可なしに使用してしまったため、訴訟につながりました。
つまり、非営利の活動であっても、他人の著作物を無断で使用することは許されないのです。
既存の映像に新たな要素を加えたリミックス動画を投稿した事例
また、既存の映像に新たな要素を加えたリミックス動画を作り、それを動画投稿サイトに投稿したクリエイターが著作権侵害で訴えられた事例もあります。
このケースでは、元の映像からの改変が十分でなかったという点が問題となりました。
つまり、他人の著作物を改変して新たな作品を作る場合でも、その改変が著作権侵害に当たらない程度であることが求められているのです。
何をすれば著作権侵害になるのか
では具体的に、どのような行為が著作権侵害になるのでしょうか。
ここでは、よくある著作権侵害の例をいくつか紹介します。
まず、他人の著作物を許可なく使用したり、元の作品を認識できないほどに改変しない限り、それを新たな作品として公開したりすることは著作権侵害になります。
これには、他人の楽曲や映像を一部でも含む動画を投稿する行為も含まれます。
次に
- 商標や会社のロゴ
- 人物の肖像
なども著作権が発生するため、これらを許可なく使用することも著作権侵害にあたる可能性があります。
無許可での使用はもちろん、改変した作品がオリジナルとなったとしても、その使用が許可されるわけではありません。
さらに、著作権フリーを謳う素材にも注意が必要です。
一部の素材は、使用に際して制限が設けられていることがあります。

たとえば、商用利用が許可されていない、作品の改変が禁止されている、クレジット表記が必要など、それぞれの素材についてライセンスを確認する必要があります。
前例を参考にしたベストプラクティス
これらの注意点を踏まえ、具体的に動画編集で著作権トラブルを避けるためのベストプラクティスを提案します。
それは
- 元の著作権者の許可を得ること
- フェアユース(公正利用)を理解すること
- ライセンスを確認すること
上記の3つです。
著作権者の許可を得ることは最も確実な対策です。
著作権者に直接連絡を取り、使用許可を得るか、その取扱について明確に合意を得ましょう。

フェアユースとは一定の条件下で著作権物を使用できる概念ですが、これは地域によって解釈が異なるため、その定義と適用条件を理解し、適切に活用することが必要です。
ラストに、著作権がクリアな素材を使用する際も、必ずそのライセンスを確認しましょう。
誤った使用がないように、使用条件や制限事項に十分注意し、ルールを守ることが大切です。
動画編集の著作権に関するよくある質問

動画編集の著作権に関するよくある質問について、一つ一つお答えしていきます。
動画の著作権の範囲はどこまでですか?
動画の著作権の範囲としては、例えば
- 一部分を引用する
- 独自の解説を加える
などして複数の映像を繋げた場合、その全てに著作権が発生し、原著作者の許可が無いと使用することは違法となります。
だからこそ、「フェアユース(公正使用)」という考え方があります。
これは、教育やニュースでの引用、パロディ・風刺など公益性が認められる利用方法に限り、著作権侵害とはみなされないという制度。

詳しい解釈は法律家に委ねられている部分も多いが、個々人も動画投稿の際は著作権法やYouTube等のプラットフォームが定めるルールを理解し、尊重することが求められるでしょう。
動画編集を依頼した場合の著作権は誰に属しますか?
依頼主、つまり発注者が著作権を持つことが一般的です。
ただし、詳細な条件や契約内容により異なるため、具体的な状況に応じて著作権の所在が変わる可能性もあるという点を理解しておくことが重要です。
一般的なケースでは、動画編集の依頼が著作権法上の「委任」と解釈され、完成した著作物の著作権は依頼者に帰属します。
編集者はあくまで依頼に基づいて創作活動を行うものであって、その結果生まれる著作物の権利は依頼者に帰属するというのが通常の理解です。
特別な取り決めがある場合
依頼者と編集者の間で著作権の所在について特別な取り決めがある場合もあります。
たとえば、契約内容に「著作権は編集者に帰属する」などと明記している場合は、その条項に従い編集者が著作権を保持します。
そのため、著作権の所在を明確にするためには
- 契約時にしっかりと確認する
- 必要であれば専門家に相談する
などのことが推奨されます。
著作権は著作物を使用する際の大切な要素であり、依頼主と編集者双方の利益を守るためにも、明確な取り決めが求められます。
自身の動画の著作権を譲渡する方法を知りたい
著作権譲渡の初歩として、著作権とは創作物の所有権を意味しています。
動画もこの対象に含まれ、制作者がその所有権を保有します。
そのため、動画の著作権を他人に譲渡したい場合、著作権法に従う必要があります。
著作権譲渡の手続きは専門家の助けを借りることも考慮に入れましょう。
その理由は、著作権法が専門的知識を必要とし、また譲渡契約の条項によっては後のトラブルを招くことがあるからです。
著作権を譲渡する具体的な手順
著作権の譲渡は、必ず書面で行うという点が重要です。
法律上、口頭での著作権譲渡は認められません。
書面には
- 譲渡する著作物の明確な記述
- 譲渡先の個人や法人名
- 譲渡日
- 譲渡の範囲と条件
などを詳細に記入することが求められます。
それに加えて、契約書を双方で署名・押印することで、著作権譲渡が法的効力を持つようになります。
合意が成立したらそれを第三者に証明するためにも、契約書のコピーを保存しておくことをおすすめします。
動画の著作権譲渡は一見難しく感じるかもしれませんが、一歩一歩法律を理解しながら進めれば、きっとスムーズに手続きが進行するはずです。
動画編集の二次利用とは?
動画編集の二次利用とは、もともと作成された映像を役立てて新たな動画を作り出す行為を指します。
具体的には
- 完成した動画を部分的に切り取って加工や再編集を行う
- 自分が持っている他の映像素材と組み合わせて新規に動画を作り出す
上記のことなどが対象となるでしょう。
例えば、企業の広報ビデオを作成した際、その一部をネットニュースの素材やSNSの投稿、商品紹介ページなど、全く別の形で活用するケースが一つ。

自分で作った映像なら自由に使いまわすことが可能ですが、他人の動画や商用利用の可否が不明確な素材を使う場合、使用許可や著作権法をしっかりと理解しておくことが重要となります。
動画編集の二次利用は、コンテンツ制作の現場においてはとても一般的。
一度制作した映像を複数の場面で利用することで
- 制作コストの削減
- 効率的な広告運用
- ブランディングを目指す
上記のことが可能に。
その一方で、著作権の問題に触れる可能性があるため、十分な注意が必要。
制作物を活用する際は、その原則を忘れないようにしましょう。
動画編集で著作権に引っかからないためには認識と対策が重要!

本記事では、動画編集における著作権の概念や注意点、そしてそれを避ける手法について解説しました。
著作権の侵害は、法律で保護されているため、それに反する行為は重大な罰則を伴います。
そうした背景から、自身で創出したオリジナルの素材を利用することを強く推奨します。
だが、何らかの理由で既存の著作物を用いる場合は、その使用が著作権法の範囲内であることを確認する必要があります。
具体的には、使用許可を取る、パブリックドメインやクリエイティブコモンズの素材を選ぶ等の方法が考えられます。
動画編集において、著作権侵害に巻き込まれないためには、認識と対策が二つの鍵になります。
それらは時間と労力を要求しますが、法律問題を避けるという観点から、適切な準備と理解は必要不可欠だといえるでしょう。
動画編集における著作権の位置づけ
- 動画編集作業においては、使用される映像や音楽素材などが著作物となり、それらの管理者から許可を得ることが必要。
- 動画投稿サイトで著作権侵害が発覚した場合、投稿した動画は削除され、アカウントの凍結や法的問題を引き起こす可能性があります。
- 著作権法違反は、違反の程度により最高で5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処される可能性があります。
- 1.使用したい素材が著作権保護の対象であるか確認する
- 2.著作権を保持している個人や企業に連絡を取る
- 3.文書で許可内容を残す
- 4.使用許可を得た素材の出典・著作権者を明示する
- 商用利用が可能か
- 元の作品をどの程度改変できるか
- 作品にクレジットを記載する必要があるか

 で
で